※ 学生の学年は,2025 年度の情報になります。
紹介する授業の一覧
- ネットワーク [1年次 秋学期 開講]
- 情報理論 [2年次 春学期 開講]
- データ構造とアルゴリズム [2年次 秋学期 開講]
- プログラミング実習III [2年次 秋学期 開講]
- コンピュータグラフィックス実習 [3年次 秋学期 開講]
- エンターテイメントコンピューティング実習 [3年次 秋学期 開講]
授業名:ネットワーク [1年次 秋学期 開講]
中井 美佑(情報工学課程・3年)

この授業では、インターネットをはじめとする「コンピュータネットワーク」の仕組みについて学べます。私たちが日常的に使っているネット通信が、どのようにして安全かつ効率よく行われているのかを、基本からしっかりと理解できる内容です。
IP アドレスやサブネットマスクなど、ネットワークを構成する重要な技術についても、丁寧に教えてもらえます。
授業は座学だけでなく、毎回関連する課題にも取り組むことで、学んだ内容をより具体的に深められます。たとえば、データがどのように送られ、どんな流れで相手に届くのかといった「目に見えない通信のし
くみ」も、段階的に理解できるようになっています。
はじめは専門用語が多く難しく感じることもありますが、課題を通して知識を整理したり、先生の丁寧なフィードバックを受けたりする中で、自然と理解が深まります。ネットワークの裏側を知ることは、単なる知識ではなく、今後の学びや研究、さらには日常生活の中でも役に立つ力になると感じられます。
インターネットに詳しい人はもちろん、「あまり知らないけど仕組みを理解してみたい」という人にも楽しめる授業です。身近な技術を “中から知る” ことで、新しい視点を得られる、そんなきっかけになる授業です。
授業名:情報理論 [2年次 春学期 開講]
土居 桜綺(情報工学課程・3年)

この授業では、「情報とは何か?」という根本的な問いに対して、数学や数式を使って情報を“数字”として表す方法を学べます。たとえば、「シャノンの情報量」や「エントロピー」といった考え方を使うことで、ニュースや日常の出来事など、私たちが目に見えない形で受け取っている情報を数値として扱うことができるようになるということを学びます。
高校生のときには漠然としていた「情報」というものが、式やグラフで明確に表せることに驚き、日常の見方が変わるきっかけにもなります。授業では、論理的な思考力や、難しいことを自分で調べて粘り強く理解する姿勢も自然と鍛えられます。
授業の後半になると、最初に学んだ内容をもとに、より高度な式や新しい表現が次々に登場します。そのぶん難しさもありますが、先生の丁寧な説明や、質問への対応のおかげで一つひとつの理解を積み重ねることができます。
この授業で学ぶ情報理論は、AI、通信、データ圧縮、暗号技術など、さまざまな分野に応用されています。情報工学だけでなく、言語学や物理学など他分野とも関わりがあるため、将来幅広い分野で活躍したい人にとって、非常に価値のある内容です。
数学や理科が好きな人、あるいは「身の回りの現象を数字で説明してみたい」という人に、特におすすめの授業です。
授業名:データ構造とアルゴリズム [2年次 秋学期 開講]
桂 壮輔(情報工学課程・4年)

この授業では、コンピュータが大量のデータを「速く・効率よく」処理するために欠かせないアルゴリズム(計算の手順)を学びます。たとえば、データを並べ替える「ソート(整列)」という処理について、複数のアルゴリズム(バブルソート、クイックソートなど)を比較しながら、それぞれの特徴や計算の速さの違いを理解します。
課題を通して実践的に学ぶ機会も多く、少し難しい課題にも挑戦しますが、仲間と協力しながら取り組むことで、理解を深めることができます。また、先生が実際の社会でのアルゴリズムの活用例も紹介してくれるので、「今学んでいる知識が将来どんな場面で役立つのか」をイメージしやすくなっています。
この授業では、単に動くプログラムを作るのではなく、「どうすればより効率よく動くのか」といった視点も養えます。アルゴリズムを選ぶだけで処理の速さが大きく変わることを体験し、仕組みの違いを意識しながらプログラムを設計する力が身につきます。
将来、IT分野で活躍したい人や、より高度なプログラミングに挑戦したい人にとって、土台となる力がしっかりと身につく授業です。競技プログラミングに興味がある人にもおすすめです。
授業名:プログラミング実習III [2年次 秋学期 開講]
岡 和寛(情報工学課程・3年)
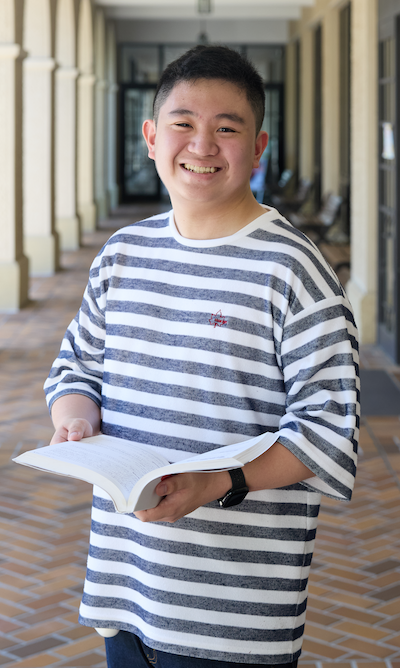
この授業では、C++というプログラミング言語を使いながら、実践的なプログラムの作り方を基礎から応用まで幅広く学べます。以前に学んだCやC++の基礎的な知識を復習しながら、オブジェクト指向や標準ライブラリなど、より高度な技術や概念にも触れていく内容です。
授業では、「オブジェクト指向」「コンパイル」「ポインタ」など、実際のプログラミングに欠かせない概念を学び、プログラムがどのように動作するのかを深く理解できます。他の言語(Python や Java)との共通点にも気づくことができ、複数の言語に対応できる柔軟な考え方が養われます。
この授業を通して、C/C++ を使ったプログラムの書き方だけでなく、それがどのように動作しているのかといった仕組みも学べます。実際に手を動かしながら学ぶことで、応用力やトラブルへの対応力も自然と身につきます。
3 年次以降の専門授業や4 年次の卒業研究では、プログラミングを必要とする場面が多くなります。この授業で得た知識やスキルは、そうした実習や研究をスムーズに進めるための大きな土台になります。プログラミングに興味がある人や、将来IT系の仕事を目指している人、数学的な仕組みへの理解が好きな人には特におすすめの授業です。
授業名:コンピュータグラフィックス実習 [3年次 秋学期 開講]
末廣 大樹(情報工学課程・3年)

この授業では、コンピュータグラフィックス(CG)の基礎から応用までを体験的に学べます。授業の前半では、展開図のイメージをつかむための工作や、影のつけ方を学ぶデッサンなど、手を動かしながら立体や光の考え方を身につけます。後半では、3D ゲームや 3DCG の制作に取り組む自由課題があり、実際に作品を作りながら CG の仕組みを深く理解できます。
私はC++を用いた3Dゲーム制作に挑戦し、Blenderという3Dソフトで作成したキャラクターに骨組み(リギング)を入れ、動かすモーションをゲーム内に取り込むところまでを体験しました。制作の過程では、座標の変換や空間のイメージ力、行列の理解といった数学的な力も必要になり、3次元の考え方が鍛えられました。
もともと CG に興味があったこともあり、制作はとても楽しく取り組めましたが、3D モデルをゲームに取り込む工程は思っていた以上に難しく、ゲーム開発の奥深さを実感しました。自由課題では配布されたプログラムを自分で読み解いて改良していく形式だったため、コードを書く力だけでなく、既存のコードを理解する力も身につきます。
この授業は、3D ゲームや CG 制作に興味がある人には特におすすめです。プログラミングが好きな人はもちろん、美術や数学、ものづくりに関心がある人にとっても魅力的な内容です。受講生の誰もがクオリティの高い作品を仕上げていて、教室全体が創造力にあふれていたのが印象的でした。
授業名:エンターテイメントコンピューティング実習 [3年次 秋学期 開講]
平山 心(知能・機械工学課程・4年)

この授業では、ゲームやアプリ、映像など、コンピュータを使ったエンターテインメントコンテンツの制作に取り組みます。企画書・計画書の作成から始まり、それに沿って作品を形にしていく中で、「人に楽しさや感動を届ける」ための考え方や技術を実践的に学べます。
特に重視されるのは、コンテンツを利用するユーザー中心の考え方です。「ユーザーに何を感じてほしいか」「そのために必要な仕組みは何か」などを深く考えながら制作を進めていくことで、自分本位ではない“伝わるコンテンツ”の作り方が身につきます。授業ではこのプロセスを支えるための便利なツールも紹介され、初めての人でも着実にステップを踏んで学ぶことができます。
実習を通して得られる「ユーザー目線に立つ力」は、エンタメ制作だけでなく、プレゼンテーション、企画立案、チーム開発など、将来のさまざまな場面で活かすことができます。「何かをつくるだけで終わらせず、しっかり伝える・届ける」ことを学べる点が、この授業の大きな魅力です。
この授業は、「面白いと感じた体験を他の人にも伝えたい」「将来、企画や制作の仕事に関わってみたい」「自主制作をもっとよくしたい」と考えている人に特におすすめです。自分の想いを形にし、人に伝える力を育てたい人にぴったりの内容です。
